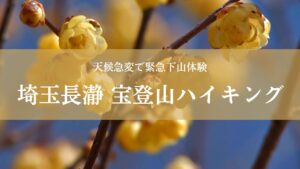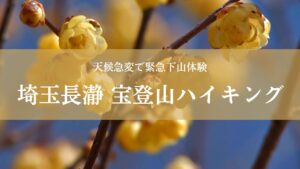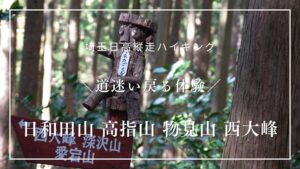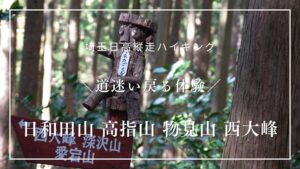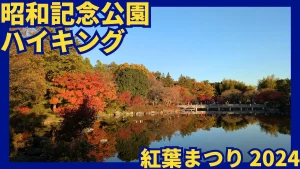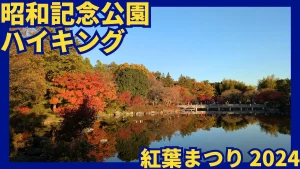今回は、飯能駅から、天覧山で富士を見て、巾着田を経て、高麗駅から帰途に着く予定です。総距離7.7km、コースタイム2時間42分、コース定数11のコースです。先週、膝が痛かった妻の様子見も兼ねて、だらだらお気楽にハイクできるコースにしました。急登は一切ないはずです。この映像の内容は、ブログでも公開しています。
埼玉飯能~日高 天覧山~巾着田 膝が不安な時でも大丈夫!お気楽ハイキング
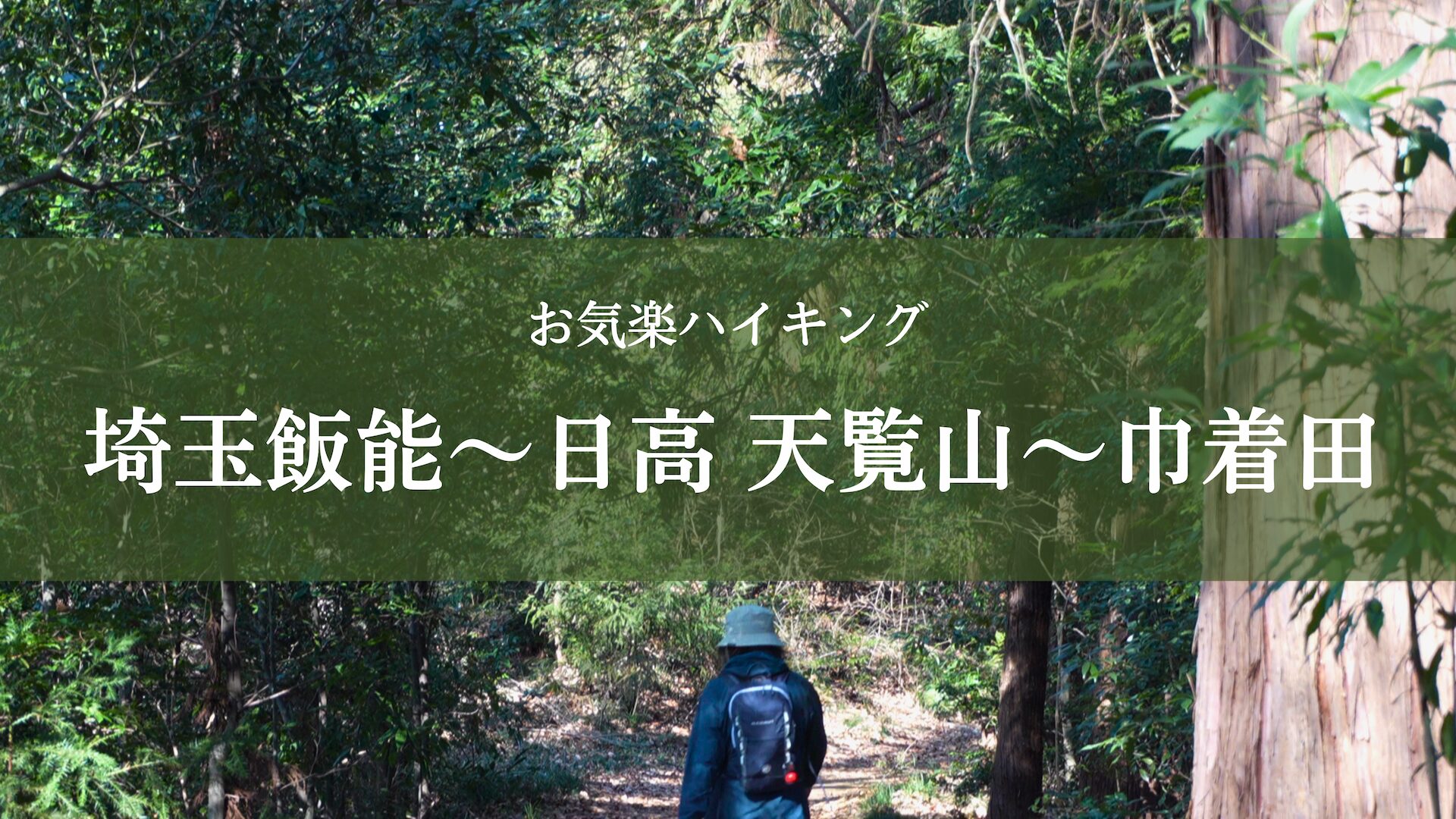
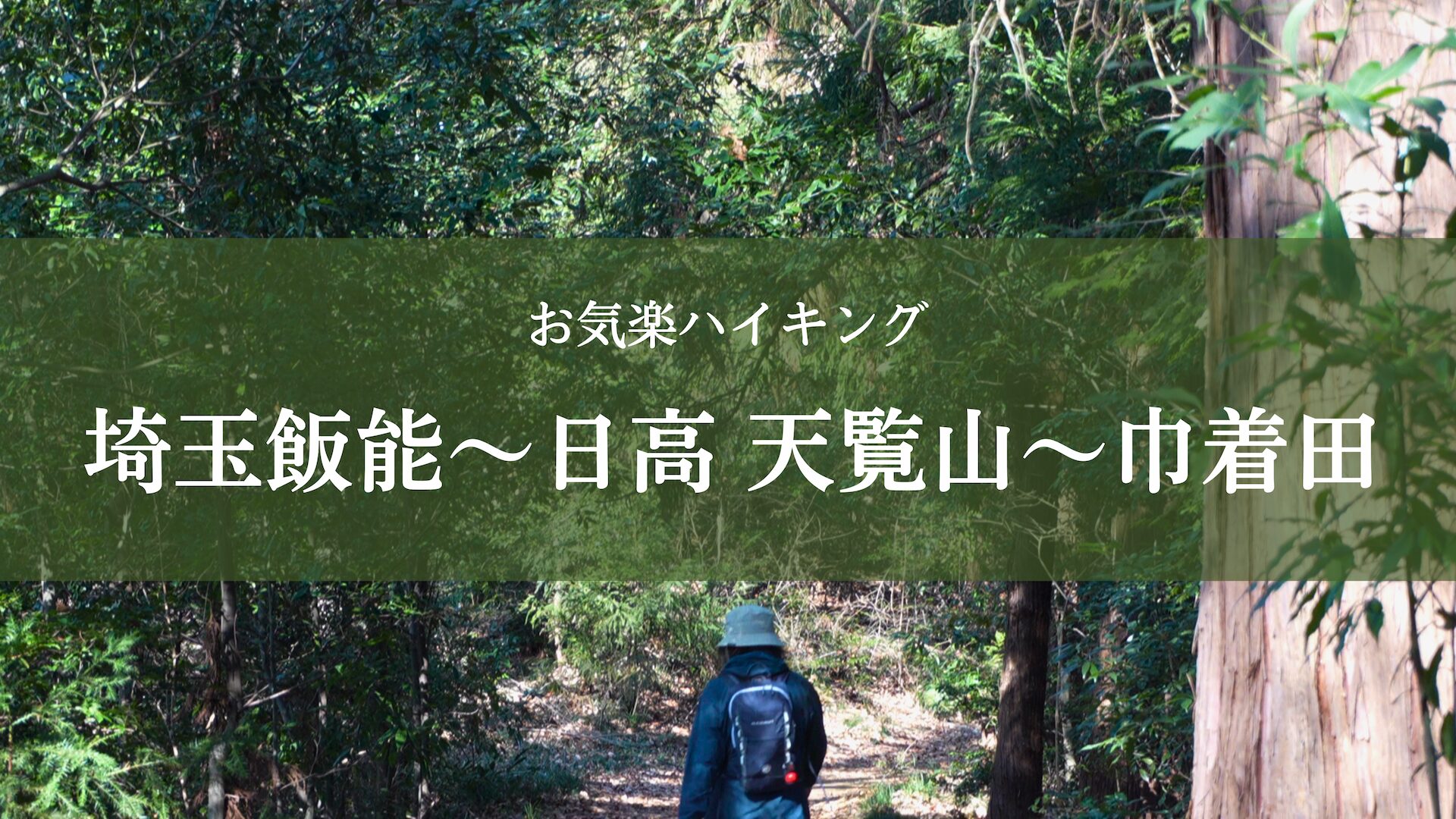
今回は、飯能駅から、天覧山で富士を見て、巾着田を経て、高麗駅から帰途に着く予定です。総距離7.7km、コースタイム2時間42分、コース定数11のコースです。先週、膝が痛かった妻の様子見も兼ねて、だらだらお気楽にハイクできるコースにしました。急登は一切ないはずです。この映像の内容は、ブログでも公開しています。